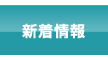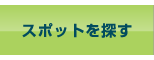目次

- »2014年3月19日
- モクヨ六地蔵塔(仙田室屋)
-
唐船峡の近くには,むくろじの大木の林があり,古くから「モクヨ山」と呼ばれている。その山に,天正10年(1582)に建てられた高さ2mの六地蔵塔と数基の五輪塔,1基の板碑がある。 六地蔵塔には,頴娃城にいた平姓池田対馬守が […]
- »2014年3月19日
- 観葉植物
-
指宿での観葉植物の栽培は大正7年,鹿児島大学農学部付属指宿植物試験場の設置とともに始まった。戦後,その生産規模は徐々に拡大,温泉熱を利用した栽培方法も研究され,昭和53年(1978)には,当時,東洋一といわれた観葉植物団 […]
- »2014年3月19日
- 徳光スイカ
-
「西瓜 當邑に出るは,皮薄くして,味甘美なり。藩人山川西瓜と称し,賞味す。」(三国名勝図会)江戸時代,すでに山川のスイカはうまいと,評判だったようだ。現在も「徳光スイカ」のブランドで人気がある。その秘密は,開聞岳にある。 […]
- »2014年3月19日
- 菜の花
-
「いぶすき菜の花マラソン」でもおなじみの,菜の花。指宿との関係はずいぶんと古く江戸時代までさかのぼる。天保3年(1832)特産品の一つとして菜種に注目していた調所笑左衛門広郷は,骨粉肥料を配り品質を向上させ,袋詰め方法を […]
- »2014年3月19日
- 揖宿神社の浜下り
-
旧暦の3月20日は,揖宿神社の浜下りの日。今は2年に1度,5月3日に行われ,祭典の後,揖宿神社から宮ヶ浜までの約3.8㎞を,高さ4mの猿田彦の人形山車を先頭に2時間余りかけて神幸行列する。1545年から続く伝統行事だ。
- »2014年3月19日
- 揖宿文書20点
-
指宿関連で有名な古文書に,「指宿文書」というものがある。指宿文書は,指宿を支配した指宿氏が伝える鎌倉時代以降の重要文書だ。内容は,鎌倉幕府から出された裁判の判決文や,揖宿郡内で度々激戦があったことを記すものなど,様々。中 […]
- »2014年3月19日
- さまふり
-
さまふりは,高野原地区に伝わる踊りで,揖宿神社とゆかりがある。その語源は,歌詞の中に出てくる人物の「イキ」な「サマ」,いわゆる伊達男振りに由来するそうだ。この歌は,参勤交代の際,長旅の慰めにうたわれたと言われる。出場の際 […]
- »2014年3月19日
- 山川漁り節
-
山川漁り節は,不漁の折に祭事を行い,大漁を祈願して「漁り節」を歌いはやしたという「沖得祭(おきえまつり)」の故事に由来している。山川漁り節は,この「漁り節」を再編したもの。漁船の出港や大漁の様子,鰹を切る様子を踊りで表現 […]
- »2014年3月19日
- 『薩南民俗』
-
指宿の伝統行事や習俗は,『薩南民俗』に詳しく報告されている。これは,指宿高校教諭として赴任した国分直一氏や小野重朗氏らの指導により,指宿高校郷土研究部の報告書として,昭和33年の第1号から第16号まで刊行されたもの。現在 […]
- »2014年3月19日
- 中川ごちょう踊り
-
南九州には太鼓踊りが多くあるが,指宿には,中川地区にごちょう踊が伝承されている。この踊りには唄はなく,色鮮やかな陣羽織風の衣装を身にまとった舞い手が,太鼓や鉦(かね=平たい円盤状の打楽器)を打ち鳴らしながら勇ましく舞う。 […]
- »2014年3月19日
- 鬼火焚き
-
鹿児島の各地で行われる正月の伝統行事の一つ。夕日が沈む午後6時ごろ,七草祝いの子どもたちが無病息災を願って火をつけると,「パンパン」と竹の節が弾ける音が響く。黒く焼けた薪は家に持ち帰り,魔よけにしたり,七草がゆの火種にし […]
- »2014年3月19日
- 馬方踊
-
成川の前薗馬方踊は疱瘡踊とも呼ばれる。江戸時代に疱瘡(天然痘)が大流行したことがあったが,神に踊りを奉納し,平癒を祈願したところ効果があり,薩摩藩主島津義弘がこれにあやかりたいとして広めたとも言われている。踊りの内容は, […]
- »2014年3月19日
- 小牧四ツ竹踊り
-
「四ツ竹」とは,平たい2枚の竹片を両手に重ねて持ち,歌に合わせて手を開いたり,閉じたりしながら打ち鳴らす素朴な楽器のこと。小牧に伝えられている。これを使って踊るのが小牧四ツ竹踊りだ。服装は,鉢巻,かすりの着物にたすき,草 […]
- »2014年3月19日
- 成川そば切り踊
-
そば切り踊は,鎌でそばを刈り取り,めぐり棒で実を落とし,臼で引いてそば切りを作る一連の作業を,方言を使ってユーモラスに表現するユニークな踊り。その昔,山川成川の前薗地区にやってきて,村人の平安を祈祷してくれていた祈祷師「 […]
- »2014年3月19日
- 慶固遺跡
-
2006年,開聞岳からわずか5㎞の場所で,874年3月25日の噴火でパックされた畑の跡が見つかった。火山礫は少なくとも4mは積もっていたようだ。畑を営んだ人々の集落は,埋没し壊滅的な被害を受けたに違いない。逃げることがで […]
- »2014年3月19日
- カニハワセ
-
カニハワセは,3月3日の桃の節句行事。山川地方では,床の間に青竹と杉の葉で杉垣の雛壇を作り,土人形を置いて,松枝や浜砂,石,貝殻などで浜の風景を作り,このような雛壇を前に,親類ななどを招いて祝いの宴を開いていた。岡児ヶ水 […]
- »2014年3月19日
- イシナト
-
イシナトは尾掛で行われる正月の子どもの遊び。元旦から七日までの適当な日に,子どもらが竹の弓矢を持って集まり,ダイダイの実を射る。ダイダイを転がすとき,「イシナト,イシナト(ニシナト)何じゃ無か,飛ベヨ」とはやし,射当てた […]
- »2014年3月19日
- 唐人踊(中小路・宮ノ前)
-
江戸時代,薩摩藩は,琉球に貢物を納めさせていた。その際,次の船が琉球から来るまで,人質として鹿児島に残された人々がいたそうだ。唐人踊は,これらの人々が指宿にやってきて,唄い踊ったものだと伝えられている。中小路地区のものは […]
- »2014年3月19日
- 棒踊り
-
棒踊りは鹿児島が生んだ独特の芸能。田植え前後の豊作を祈る踊りと伝えられているが,一説には,島津義弘ひきいる薩摩との朝鮮半島と戦いの後,その帰国祝いとして始まったとも言われている。6尺棒や3尺棒を持った踊り手たちが,歌に合 […]
- »2014年3月19日
- ダセチッ
-
ダセチッとは,ハラメウチ(新婚家庭の子宝を願う行事)のこと。前年に結婚した家を子どもたちがダセ棒を持って祝福に訪れる。ダセッチ,ダセなどともいう。利永では,1月14日の日没頃,子どもたちが新婚家庭を訪れ,棒で庭の土を突き […]