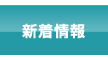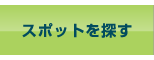目次

- »2014年3月19日
- 縄状玄武岩
-
花瀬から田﨑の海岸にみられる縄上玄武岩は,開聞岳の弥生時代の噴火で沖へどろどろ流れ出たもの。玄武岩はガラスの主成分でもある二酸化ケイ素の含有量が比較的少なく流動性が高いため,地表に流れ出た際に,障害物があるとうねうねと曲 […]
- »2014年3月19日
- 竜宮神社
-
長崎鼻灯台の北側には,竜宮神社が建てられている。祭神は豊玉姫命,海上救護の女神だ。明治44年に書かれた『山川郷土歴史』には,昔から村人が崇敬する神社があったこと,長崎鼻が「竜宮鼻」と呼ばれていたことがわかる。平成23年に […]
- »2014年3月19日
- ソテツ自生地
-
竹山や長﨑鼻は,大隈半島の佐多・内之浦とともにソテツ自生地の北限として知られ,国の天然記念物に指定されている。ソテツ類は,古生代末から中生代,“恐竜の生きた時代”に最も栄えた裸子植物。現世のものは「生きた化石」とも言われ […]
- »2014年3月19日
- 俣川洲(またごし)
-
竹山の南に浮かぶ俣川洲は,竹山と同様にできた火山の名残だ。海水で削られたトンネル(海食洞)がポッカリと空いており,その大きさは小舟が通り抜けられるほど。江戸時代にはすでに,「俣川洲」と表記されていたようだ。「俣」は川や道 […]
- »2014年3月19日
- 鏡池
-
直径140m,深さ約14m。鏡池は,約5,700年前の噴火でできた火口に水がたまったもの。鏡池には,こんな伝説がある。 「その昔,誤って池に落ち上がってこない小坊主を助けるため,和尚が霊力で池の水を北の窪地に移すと,底に […]
- »2014年3月19日
- 玉の井
-
神代の昔から日本最古の井戸と伝えられている。神話によると,神代の時代,この辺りは竜宮界で,玉の井は竜宮城の門前の井戸だったという。龍神の娘豊玉姫が朝夕汲まれた井戸でもあり,姫はこの井戸端で彦火々出見尊(山幸彦)と出会い, […]
- »2014年3月19日
- 上仙田東屋敷供養塔群
-
仙田瓦ヶ尾一帯は,昔,仙田村東屋敷と呼ばれていた。ここには,この地に住んでいた六兵衛(戒名は月秋浄井上座)が建立したと言われる六地蔵塔1基,五輪塔15基,板碑6基,その他多数の供養塔の残欠が残っている。元和8年(1622 […]
- »2014年3月19日
- 松原田観音寺跡石塔群
-
開聞古事縁起によると,昔,この一帯に観音寺という寺が建てられていたという。昭和2年,公民館敷地を整地するときに,埋もれていた六地蔵塔や五輪地蔵塔,板碑等の供養塔を掘り出して保存。昭和59年,公民館の改築に伴って現在地に移 […]
- »2014年3月19日
- 伏目海岸
-
伏目海岸の白いビーチは,火山活動を体験できる,日本でもまれなビーチ。海岸にそびえる白い崖は,池田湖が噴火した際に積もった火砕流堆積物だ。この崖が砕けて砂浜をつくっているため,伏目海岸は白っぽい。そして,砂むし温泉があるこ […]
- »2014年3月19日
- 上野神社周辺供養塔群
-
上野神社周辺には,「上野どんの墓」と呼ばれる百数十の供養塔群がある。供養塔群の中心には,比翼塚(愛し合って死んだ男女を一緒に葬った塚)ともみられる2墓の宝塔があり,し周囲に五輪塔や板碑等が並び,丘をつくっている。
- »2014年3月19日
- 頼宋塚・九郎塚
-
地元の人々に頼宋塚(デスドン),九郎塚(クロドン)と呼ばれる2つの塚には,次のような話が伝えられている。「頴娃6代城主兼堅の子・九郎と,兼堅の側室の子・小四郎という弟との間で,頴娃家の相続争いが起こった。小四郎の母親は九 […]
- »2014年3月19日
- 菅山の方柱板碑
-
菅山の方柱板碑は,天文18年(1549)に建立された。碑の正面に直径5cmの「○」(円相:えんそう)が彫られ,その中に「心」の字が刻まれている。この「○」は禅宗で悟りのシンボルとして描かれるもので,心が完全に満たされてい […]
- »2014年3月19日
- 松梅蒔絵櫛笥附属品竝目録共 一合
-
松梅の蒔絵で飾られた女性の化粧箱。通称「玉手箱」。中には,小さな櫛が11本,小さな壺が1つなど23個の化粧道具が入っている。化粧箱の目録には,大永3年(1523)とあり,室町時代の高貴な女性が使ったものと推測される。国指 […]
- »2014年3月19日
- 鬼門平の鉱山
-
鬼門平に沿って,金鉱床が存在する。明治から昭和30年頃まで多くの鉱山が開発され,たいへんな賑わいをみせたという。そのなかの一つに,1844年(弘化元)に発見された大谷鉱山がある。当時の技術では採鉱は困難を極め,4年後には […]
- »2014年3月19日
- 枚聞神社琉球扁額7点
-
今から約400年前,薩摩藩は琉球王国を統治し,慶長18年(1613)からは、琉球使節団の派遣が始まった。枚聞神社には,「徳偏海天(徳は海と天にゆきわたる)」等と書かれた,7枚の琉球扁額(へんがく)が奉納されている。「海門 […]
- »2014年3月19日
- 噴気変質帯
-
池田湖の北東2km,標高約200mの山中にある噴気変質帯。熱水と火山ガスの作用によって,安山岩や安山岩質の凝灰岩が,白っぽいカオリンなどの粘土鉱物に変化している。熱を帯びた地面からは,もうもうと煙が立ち上る。麻袋に生卵を […]
- »2014年3月19日
- 鬼門平
-
鬱蒼とした木々,その間に見える奇岩。江戸時代,「唐畫山水に似たりと称ず」と中国の山水画に例えられ,椋鳩十が「屏風岩」と表した鬼門平。高さ約200~300m,長さ約10km。池田湖の北西に延びる断崖は,約10万年前の大噴火 […]
- »2014年3月19日
- 枚聞神社神舞
-
古文書等によると,枚聞神社には,かつて数十種の神舞があったそうだ。現在は,剣の舞、南方の舞、中央の舞、鈿(うずめ)の舞の4つが青年団によって伝承されている。神舞は,毎年10月14日の例大祭の前夜祭で,巫女による浦安の舞と […]
- »2014年3月19日
- 開聞岳
-
開聞岳は,市の南西部に位置する標高924mの活火山。今から約3,700年前の縄文時代に誕生した。複数回の噴火で溶岩や火山砕屑物などが積み重なって形成された円錐状の成層火山の頂上部に,粘性の強いマグマが盛り上がりできた溶岩 […]
- »2014年3月19日
- 枚聞神社本殿
-
開聞岳の麓に鎮座する,薩摩国の一の宮,枚聞(ひらきき)神社。神社の縁起には,和銅元年(708)の創建と記されている。開聞岳は「開聞神」とも表記され,噴火は開聞神の祟りと見なされており,枚聞神社がこれを祀っていた。現在の本 […]