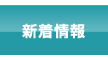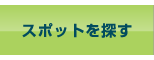目次

- »2014年3月19日
- 成川遺跡
-
成川遺跡は,弥生時代の中頃から古墳時代に至る巨大な墓地。昭和32年に発見され,発掘調査の結果,土葬された300体を超える人骨に加え、鉄製の刀や剣などおびただしい数の副葬品が見つかった。古墳は造られておらず,土こう墓(土葬 […]
- »2014年3月19日
- 鰻池
-
昔話では「その昔,鰻池の水を利用して水田を造ろうと池の畔で開削工事を始めたところ,池の底から大ウナギが現れ,開削した場所に横たわり水が流れ出るのを塞いでしまった。村人がこれを切り裂いたところ,大ウナギは片身のまま池に逃げ […]
- »2014年3月19日
- 鰻のスメ
-
スメは,鰻地区の多くの家庭にある火山性天然蒸気カマド。芋は約40分,卵なら5〜10分で蒸し上がる。『島津斉彬御供日記』にもスメのことが記されている。嘉永4年霜月19日晴れ・・・「鰻の池廻り1里余もあり,蒼浪岸をひたす辺り […]
- »2014年3月19日
- 水迫遺跡
-
水迫遺跡は指宿市のほぼ中央,標高126mの尾根上にある。水迫遺跡では,約1万5千年前の石器とともに,竪穴建物跡や炉跡,石器を作った作業場や道の跡などが発見されている。約1万5千年前の生活痕跡がこれほどまとまって見つかった […]
- »2014年3月19日
- 震洋基地跡等 戦跡
-
第二次世界大戦中,指宿には二つの震洋隊が置かれた。一つは山川長崎鼻の第53震洋隊,もう一つは指宿田良の第106震洋隊である。震洋は全長5〜6mのベニヤ板製モーターボート。爆薬を積んで敵に突っ込む特攻兵器だ。魚見漁港近くの […]
- »2014年3月19日
- 魚見岳(うおみだけ)
-
その昔,漁師たちが頂上から魚の影を確かめたといわれる魚見岳。南側から望む姿がハワイのダイヤモンド・ヘッドに似ていることでも知られている。標高は約200m。10万年以上前にできた火山の名残だ。南東側は断崖絶壁で,溶岩とそれ […]
- »2014年3月19日
- 天狗岩
-
魚見岳の8合目にある,注連縄が巻かれた,通称「天狗岩」。魚見岳には天狗が住むという伝説があり,この天狗は赤い色のものが大嫌いなため,山には赤色の花が咲かないという。また,赤い色の着物を着て山に登ろうものなら,天狗に蹴落と […]
- »2014年3月19日
- 天狗の祠
-
天狗岩の背後の山中には,高さ2mほどの天狗の祠がある。素材は山川石。祠の中の角柱には「大天狗」の文字。豪商濱﨑太平次が,あるいは黒岩藤兵衛が建立したともいわれるが定説はない。祠の中には,寛永通宝の古銭が相当量入っていたと […]
- »2014年3月19日
- 無足明神(むそくみょうじん)関連石造物
-
尾掛地区には明治時代まで,大隅から流れ着いた蛇を祀る「無足明神」があった。ここで, 蛇を模して足を隠した舞手が谷から現れ,神木にまといつく「無足舞」が行われたという。現在は,『三国名勝図絵』に描かれた手水鉢と思われる石造 […]
- »2014年3月19日
- 揖宿神社本殿・舞殿・勅使殿
-
揖宿神社は1200年以上も前の古代から崇敬される神社。現在の社殿は,弘化4年(1847)に薩摩藩主の島津斉興が建造したものだ。花崗岩で造られた鳥居は,嘉永元年(1848)に斉興の命令で,大隅半島の根占から運ばれて建てられ […]
- »2014年3月19日
- 揖宿神社の社叢
-
揖宿神社には,推定樹齢700年以上といわれるクスノキの大樹が8株も群生している。さらにクスノキの周りには,エノキやイチョウなど,高さが20mを超える大木がまとまって生えている。県内でも珍しい社叢である。
- »2014年3月19日
- 能面
-
揖宿神社には,能面や神輿など数多くの宝物が伝えられている。特に,室町時代中期の作とされている尉面(男の老人の顔),姫面(若い女性の顔),狂言面の三面は,日本で能や狂言が完成されたころの貴重なものだ。神社では「能」や「狂言 […]
- »2014年3月19日
- 調所笑左衛門広郷が寄進した揖宿神社の手水鉢
-
薩摩藩の財政が行き詰まる中,文政11年(1828),調所笑左衛門広郷は財政改革主任に大抜擢された。藩には500万両もの借金があったが,国産品の販売と唐物貿易を拡大し収入を増やしたり,借用書の借金の返済期間を250年に書き […]
- »2014年3月19日
- 揖宿神社前田ノ神依代椋ノ木
-
揖宿神社前の田の神は,ムクノキを神体としている。これは樹木に田の神が宿ると伝えられている珍しい事例で,田の神の石像が作られる前の信仰のかたちを伝えるものだ。揖宿神社では,昭和28年頃まで,このムクノキの下でお田植え祭りが […]
- »2014年3月19日
- 殿様湯跡
-
現在残っている殿様湯跡は,天保2年(1831)に第27代薩摩藩主島津斉興によって二月田に設けられたものだ。浴槽は,お湯が4つの湯つぼを次々に回って適温になるように工夫されている。浴室には洋風のタイルが使われており,大変豪 […]
- »2014年3月19日
- 湯権現(ゆのごんげん)
-
殿様湯の南側にある湯権現は,濵崎家第5代の太左衛門が創建した。権現とは,仏が日本の神に姿を変えて現れること。「湯権現」という名前は,温泉のさまざまな効き目が神仏の力によるものという信仰の表れであろう。
- »2014年3月19日
- 嘉永5年の水道管「石樋(いしどい)」
-
嘉永5年頃(1852),約3km離れた池田湖付近から二月田温泉まで,石樋を使って飲料水を引く工事が行われた。安政4年(1857)には,二月田温泉に湯治に来ていた島津斉彬が,周辺は水の便が悪く田んぼが少ないことを見て,池田 […]
- »2014年3月19日
- 弥次ヶ湯古墳
-
弥次ヶ湯古墳は,国内最南端の古墳。5世紀後半〜6世紀前半のものと考えられる。円墳で,墳丘の直径は約17.5m,周りを巡る溝の幅は約2mを測る。弥次ヶ湯古墳の発見までは,川内川より南の薩摩半島は古墳の「空白地帯」と考えられ […]
- »2014年3月19日
- 敷領遺跡
-
敷領遺跡は,十町小字敷領一帯に広がる。「糄」(やきごめ),「智」と墨で書かれた土器や硯(すずり),整然と並ぶ建物群などが発見されている,奈良〜平安時代の役所の候補地だ。中でも注目されるのは,将棋の駒のような形をした「甲臺 […]
- »2014年3月19日
- 第八代濵﨑太平次正房墓
-
第8代濵﨑太平次は,文化11年(1814),湊のヤマキという商家に生まれた。薩摩藩の後ろ盾もあって造船業や海運業で活躍。日本最大級の船団を率いて巨万の冨を築き,調所笑左衛門の右腕として,薩摩藩の財政再建に大きな役割を果た […]