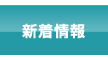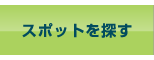目次

- »2014年3月19日
- 二反田川石積堤防
-
殿様湯跡前の二反田川の川岸には,天保14年(1843)に造られた石積みの堤防が残っている。当時は,二反田川の河口から約3kmにわたって7段の石積みが続いていた。試算でも約6万個の石が必要になる大工事だ。島津の殿様は,屋形 […]
- »2014年3月19日
- 島津斉彬公堀井碑新旧二基
-
安政5年(1858),二月田に湯治に来た島津斉彬は,指宿の大干ばつを目の当たりにし,将来に備えて,東郷吉左衛門らに97の井戸を掘らせた。翌年,井戸を掘った記念としてこの掘井碑が建立された。その後,碑文が読みづらくなったた […]
- »2014年3月19日
- 上西園のモイドンなど民俗神
-
モイドンは,「森」に「殿」という敬称をつけたもので,森神という意味。その神体が樹木であることが特徴だ。指宿は県下で最もモイドンが多く,40近い例がある。その一つ,上西園のモイドンは東方道上にある。このモイドンの依代はアコ […]
- »2014年3月19日
- 谷山筋の大楠
-
薩摩藩では、城下鹿児島からの軍事・交通連絡網が整備されていた。指宿は、谷山-喜入-今和泉-指宿-山川-頴娃-知覧へと続く谷山筋に属していた。 揖宿神社前をとおり、中福良を過ぎた辺りで、宮ヶ浜方面に曲がり、湊川へと続く道 […]
- »2014年3月19日
- 温湯の露頭展示
-
温湯では,約53,000年前,池田湖北岸の清見岳の噴火で堆積した火山噴出物の露頭を保存・展示している。地層が波形に曲がったしゅう曲や,断層など,ダイナミックな大地の動きを観察できるポイントである。
- »2014年3月19日
- 指宿橋牟礼川遺跡
-
橋牟礼川遺跡は,十二町下里にある。大正7・8年に京都帝国大学教授の濱田耕作博士らの発掘によって,開聞岳の火山灰をはさんで上から弥生土器,下から縄文土器が出土することが確認され,日本で初めて縄文土器が弥生土器より古いことが […]
- »2014年3月19日
- 弥次ヶ湯古墳
-
弥次ヶ湯古墳は,国内最南端の古墳。5世紀後半〜6世紀前半のものと考えられる。円墳で,墳丘の直径は約17.5m,周りを巡る溝の幅は約2mを測る。弥次ヶ湯古墳の発見までは,川内川より南の薩摩半島は古墳の「空白地帯」と考えられ […]
- »2014年3月19日
- 敷領遺跡
-
敷領遺跡は,十町小字敷領一帯に広がる。「糄」(やきごめ),「智」と墨で書かれた土器や硯(すずり),整然と並ぶ建物群などが発見されている,奈良〜平安時代の役所の候補地だ。中でも注目されるのは,将棋の駒のような形をした「甲臺 […]
- »2014年3月19日
- 第八代濵﨑太平次正房墓
-
第8代濵﨑太平次は,文化11年(1814),湊のヤマキという商家に生まれた。薩摩藩の後ろ盾もあって造船業や海運業で活躍。日本最大級の船団を率いて巨万の冨を築き,調所笑左衛門の右腕として,薩摩藩の財政再建に大きな役割を果た […]
- »2014年3月19日
- 揖宿光明禅寺の木像阿弥陀如来立像
-
光明禅寺に安置されている阿弥陀如来立像は,鎌倉時代の製作様式を引き継いだ作品で,中央の仏師の作品と考えられている。穏やかな面立ちと優美な衣の表現が印象的で,像の全面に黒漆が,その上から赤色の顔料が塗られた丁寧な造りである […]
- »2014年3月19日
- 豊玉媛神社等棟札8点
-
豊玉媛神社(中宮大明神)の棟札は,神社の社殿,鳥居,仁王像,宝殿の造営や再興に伴う由緒や,建築者・大工の名などを記したものだ。最も古いものは天文13年(1544),新しいものは幕末に向かう文政5年(1822年)に描かれた […]
- »2014年3月19日
- 今和泉地区の町割り
-
今和泉島津家屋敷跡である今和泉小学校周辺には,江戸時代の風情を残す町割が残っている。第3代忠厚と第4代忠喬が隠居していた屋敷は,豊玉媛神社とJR枕崎線の中間付近にあって,当時の屋敷跡の門構えを見ることができる。 ちなみに […]
- »2014年3月19日
- 宮ヶ浜港防波堤(捍海隄)
-
宮ヶ浜の海岸にある,三日月形の防波堤(捍海隄:かんかいてい)。指宿小学校に残る石碑,指宿捍海隄記には,この防波堤建設のいきさつが記されている。「宮ヶ浜の海は遠浅で,船を安全に停泊させるところがなく,台風で船が転覆する恐れ […]
- »2014年3月19日
- 湊川橋
-
湊川橋は,江戸時代に造られた石橋。石を丁寧に加工し,それをアーチ状に組み合わせている。第27代薩摩藩主島津斉興の家老であった,調所笑左衛門広郷が,肥後の石工,岩永三五郎を招いて完成させたものという。アーチには天保15年( […]
- »2014年3月19日
- 宮ヶ浜のアコウ
-
宮ヶ浜の報国神社の境内には,日本一のアコウの巨木が生えている。幹周り14.6m,推定樹齢300年。大きさもさることながら,長い年月の間に,色々な植物が寄生し,共生しているのも特徴だ。色濃く緑が茂ったアコウは海上からも目立 […]
- »2014年3月19日
- 松尾城跡
-
松尾城は,鎌倉時代から江戸時代初期までの400年間,指宿の政治の中心を担っていた城。自然地形を巧みに利用し,それに手を加えながら空堀や土塁を築いて防御を固めている。山城であり,かつ錦江湾に面した海城でもある点が特徴だ。最 […]
- »2014年3月19日
- 宮ヶ浜の商家群
-
宮ヶ浜の国道226号沿いには,明治から大正にかけて建てられた風格漂う商家群がある。漆喰塗りの壁や段状になった屋根の造りが特徴的で,当時の姿をよく留めている。これらの建物のうち,「丸十金物百貨店店舗」,「丸十金物百貨店蔵」 […]
- »2014年3月19日
- 長勝院址石造物(快伝銘五輪塔・方柱板碑・石造如来形坐像)
-
宮ヶ浜には,「長勝院」(ちょうしょういん)という寺に関連する五輪塔と板碑が残っている。五輪塔のある場所には元々,長“松”院という名前の寺があったが,慶長14年(1609年),琉球出兵の際に,島津義弘が息子・家久の戦いの勝 […]
- »2014年3月19日
- 木造観音立像三体
-
西方久保にある木造聖観音立像三体は,廃仏毀釈の際,地元の青年たちが隠し守ったもの。それぞれ造られた時期が異なり,右端のものは,平安時代後半に造られた作品といわれ,南薩で最古とされる。中央のものは,室町時代の作品,左端のも […]
- »2014年3月19日
- 久保庵上の方柱板碑
-
正面をみると,禅宗の悟りのシンボル「○」の中に「妙」の文字が刻まれている。碑文には「松尾城の城主である津曲美濃守(つまがりみのうのかみ)が,天文16年2月20日から大みそかまでの間,僧侶10人に法華経の経典千部を全部読ま […]