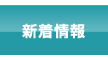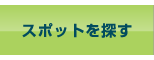目次

- »2014年3月19日
- オクラ
-
原産地はアフリカ北東部といわれるオクラは,日本に明治初期に入ってきた。指宿での本格的な栽培は昭和43年から。現在ではそら豆同様に生産量日本一となった。オクラはその形から「レディース・フィンガー(貴婦人の指)」とも呼ばれて […]
- »2014年3月19日
- 小牧四ツ竹踊り
-
「四ツ竹」とは,平たい2枚の竹片を両手に重ねて持ち,歌に合わせて手を開いたり,閉じたりしながら打ち鳴らす素朴な楽器のこと。小牧に伝えられている。これを使って踊るのが小牧四ツ竹踊りだ。服装は,鉢巻,かすりの着物にたすき,草 […]
- »2014年3月19日
- 菜の花カンパチ
-
鹿児島県は養殖カンパチの生産量が日本一,全国シェアの55%を占める。山川湾でもカンパチの養殖が行われている。ブランド名は「いぶすき菜の花カンパチ」。カンパチの稚魚は,春に山川湾に運ばれてくる。大きさはまだ9㎝前後とかわい […]
- »2014年3月19日
- 漁業
-
(財)水産物市場改善協会の調べによれば,日本で食べられている魚は,加工品も含めて256種類だそうだ。平成21年度,指宿漁港で水揚げされた魚はカツオ類,マグロ類,サバ類を中心に約100種類と豊富。海の豊かさの現れだ。身近な […]
- »2014年3月19日
- 宮坂田踊り
-
揖宿神社のある宮地区には,270年の伝統がある坂田踊が伝わっている。歌詞に遠州浜松,富士山などの地名が出てくることや,武士の装束をしていること等から,江戸時代に島津氏の参勤交代の上り歌として,長旅の疲れを慰めた事に由来す […]
- »2014年3月19日
- 唐人踊(中小路・宮ノ前)
-
江戸時代,薩摩藩は,琉球に貢物を納めさせていた。その際,次の船が琉球から来るまで,人質として鹿児島に残された人々がいたそうだ。唐人踊は,これらの人々が指宿にやってきて,唄い踊ったものだと伝えられている。中小路地区のものは […]
- »2014年3月19日
- 製塩
-
成川浜にそびえ立つ1本の煙突は塩づくりの名残だ。指宿での製塩の始まりは大正11年。豊富な温泉に着眼した黒川英二氏は,温泉熱を利用し水分を蒸発させる製塩を開始した。その後,温泉熱利用製塩には限界が見え,昭和34年,真空タン […]
- »2014年3月19日
- 山川漬②〜大壺〜
-
山川港の周辺を散策すると,民家の庭先で,高さ1mはあろうかという大壺を見かけることがある。山川漬を作るのに使われていた壺だ。山川漬は「唐漬」とも呼ばれる。中世の頃から国際貿易港として栄えた山川港。港の近くには唐人町と呼ば […]
- »2014年3月19日
- 虚無僧踊り
-
虚無僧踊りは,虚無僧姿の踊り手の両側に,長刀と鎌をもった武士にふんした踊り手がならび,互いに向き合って打ち合う変化の多い踊り。きびきびとした踊りの中で,白い虚無僧の姿がひときわ引き立つのが特徴だ。
- »2014年3月19日
- 山川本枯れ節
-
全国のカツオ節の約75%は鹿児島で作られている。そのうち約36%が山川で,全国第2位。1位は枕崎市で約39%を占める。さて,日本料理の味の決め手はなんといってもダシ。特に高級料理店では,ダシに最大限の神経がはらわれると聞 […]
- »2014年3月19日
- 士官節
-
日清・日露戦争のころ,兵士の運を祈って,地区の人々が着物姿で太鼓や三味線で伴奏しながら踊ったと伝えられている。戦後は,新築の棟上げやお伊勢講の時などに,細田西集落を中心に踊られていたという。それが途絶えてしまい,平成12 […]
- »2014年3月19日
- 山川漬①〜伝統的な作り方〜
-
伝統的な山川漬の製法は独特だ。使われるのは繊維が多く歯ごたえのいい練馬大根。これを泥つきのまま一か月ほど干す。泥つきのまま干すのは,大根の表面が傷むのを防ぐためだ。「ネクタイが結べる」程にしなびたら,海水の入った木臼に入 […]
- »2014年3月19日
- 山川漁り節
-
山川漁り節は,不漁の折に祭事を行い,大漁を祈願して「漁り節」を歌いはやしたという「沖得祭(おきえまつり)」の故事に由来している。山川漁り節は,この「漁り節」を再編したもの。漁船の出港や大漁の様子,鰹を切る様子を踊りで表現 […]
- »2014年3月19日
- 玉利奴踊
-
奴踊りは,玉利に伝えられている郷土芸能。16代島津家当主島津義久が肥前国島原城主との戦で勝利し,その祝いとして,揖宿神社に奉納されたのが始まりと伝えられている。14,5名の男踊りで,きびきびした動きの中にもユーモアを交え […]
- »2014年3月19日
- 開聞しだら節
-
川尻に伝えられる郷土芸能。開聞山麓の岩屋で鹿から生まれた瑞照姫(ずいしょうひめ)は,13歳の時,大宮姫と名を改め,天智天皇の后となった。大宮姫の美貌と出世をねたんだ女官たちは,ある雪の日,雪合戦に姫を連れ出した。雪合戦の […]
- »2014年3月19日
- カニハワセ
-
カニハワセは,3月3日の桃の節句行事。山川地方では,床の間に青竹と杉の葉で杉垣の雛壇を作り,土人形を置いて,松枝や浜砂,石,貝殻などで浜の風景を作り,このような雛壇を前に,親類ななどを招いて祝いの宴を開いていた。岡児ヶ水 […]
- »2014年3月19日
- 砂むし温泉
-
「潮が引いている朝方,あなたが一パルモ(約22㎝)掘れば,生温かい湯を感ずることであろう。そこに年寄りらが穴を掘り,朝夕,日の出や日没の潮が満ちてくるとき二時間ほど身体を横にして入浴している。」『日本報告』には砂蒸し温泉 […]
- »2014年3月19日
- 脇浦古琴節
-
古琴節は脇に伝えられている。歌詞は,夫婦でお伊勢参りをして,子どもの疱瘡(天然痘)が治るように祈願をしている事などから,県内各地で踊られている疱瘡踊の唄に類似性を見いだすことができる。疱瘡踊は日本でも珍しい芸能。昔,天然 […]
- »2014年3月19日
- 手拍子踊り(田中・谷村)
-
田中地区,谷村地区には手拍子踊りが伝わっている。 歌には「阿波の徳島」「三邦丸(みくにまる)」「花の名寄(なよせ)」の3曲がある。「三邦丸」の歌は薩摩藩が慶応元年(1865年)に英国から購入し,商船として用いられた蒸気船 […]
- »2014年3月19日
- 横瀬遺跡
-
弥生時代,「卑弥呼の鏡」などと呼ばれるように,鏡と言えば有力者の持ち物であった。青銅製の鏡は古代中国に起源をもつ権威の象徴。その鏡のかけらが横瀬遺跡から出土している。専門家によれば,中国製の鏡をまねて国内で作られた可能性 […]