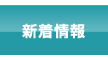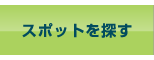目次

- »2014年3月19日
- 電照ギク
-
キクは,日照時間が短くなると芽をつけ開花する性質がある。これを利用し開花時期を調節するのが電照ギクだ。人工的に光をあてると,キクは昼の時間が長いと勘違いして,花になる芽をつけず生長を続ける。そして電気を消すと,すぐに芽が […]
- »2014年3月19日
- 指宿たばこ
-
「慶長の初年その種子を得て,薩摩の国揖宿郡指宿の里に植えしものは日本煙草栽培の濫觴にして,島津氏その種子を得て其の親戚なる京都近衛家に贈り,始めてこれを山城の花山に植ゆ。故に名づけて花山煙草広がるという。」『薩藩文化』, […]
- »2014年3月19日
- 畜産
-
鹿児島は全国第2位の畜産県。指宿の畜産をみると,明治十7年(1884)の「鹿児島県地誌」によは,当時の指宿村に,牛127頭,馬714頭が飼育されていたとある。現在,畜産は本市農業生産額の約38%を占める基幹産業の一つ。平 […]
- »2014年3月19日
- 薩摩つげ櫛
-
「櫛になりたや薩摩の櫛に諸国娘の手に渡ろ」県の伝統工芸品にも指定されている薩摩つげ櫛は,江戸時代,全国的にその名を知られていたという。江戸中期,宝暦治水と呼ばれる木曽川・長良川・揖斐川の治水工事に従事した薩摩藩は,膨大な […]
- »2014年3月19日
- 岩本遺跡
-
岩本遺跡は,今から約1万年前の遺跡だ。この頃の南九州では,縄ではなく貝殻で文様をつける円筒形の土器が大流行する。縄文時代というより貝文時代といった様相。南九州を代表する地域限定のいわば“ご当地土器”である。この独特の土器 […]
- »2014年3月19日
- 大園原遺跡
-
大園原遺跡では,建物の絵が描かれた土器片が見つかっている。国内最古級の建物絵画だ。時期は縄文時代後期,3,500年前から4,000年前頃。細かく観察すると,柱の線が床の線を突き抜けていることが分かった。どうやら高床の建物 […]
- »2014年3月19日
- 南丹波遺跡
-
南丹波遺跡は,丹波小学校一帯に広がる弥生時代の集落遺跡。学校の校庭から,14軒の竪穴住居や土器捨て場が見つかった。14軒のうち9軒は,竪穴の内部が複数の土壁で仕切られた平面形が花びらのような形になる「花弁型住居」。その源 […]
- »2014年3月19日
- 南摺ヶ浜遺跡
-
南摺ヶ浜遺跡では,宇宿上層式土器と呼ばれる土器片が出土している。奄美大島の宇宿貝塚で初めて見つかった土器だ。時期は縄文時代の後期。この土器は,北はトカラ列島の中之島付近,南は沖縄本島まで分布する南の土器。指宿と南西諸島と […]
- »2014年3月19日
- 中尾迫遺跡
-
中尾迫遺跡では,約1700年前の土器作り工房が発見された。土器を焼いた穴は直径約1m,深さ20㎝程度。穴の底は焼けて赤く変色していた。この穴に生乾きの土器を入れ,ススキなどの植物を覆いかぶせて焼いたものと見られている。土 […]
- »2014年3月19日
- 横瀬遺跡
-
弥生時代,「卑弥呼の鏡」などと呼ばれるように,鏡と言えば有力者の持ち物であった。青銅製の鏡は古代中国に起源をもつ権威の象徴。その鏡のかけらが横瀬遺跡から出土している。専門家によれば,中国製の鏡をまねて国内で作られた可能性 […]
- »2014年3月19日
- 松原田観音寺跡石塔群
-
開聞古事縁起によると,昔,この一帯に観音寺という寺が建てられていたという。昭和2年,公民館敷地を整地するときに,埋もれていた六地蔵塔や五輪地蔵塔,板碑等の供養塔を掘り出して保存。昭和59年,公民館の改築に伴って現在地に移 […]
- »2014年3月19日
- 縄状玄武岩
-
花瀬から田﨑の海岸にみられる縄上玄武岩は,開聞岳の弥生時代の噴火で沖へどろどろ流れ出たもの。玄武岩はガラスの主成分でもある二酸化ケイ素の含有量が比較的少なく流動性が高いため,地表に流れ出た際に,障害物があるとうねうねと曲 […]
- »2014年3月19日
- 天の岩屋供養塔群
-
開聞岳の麓にある「岩屋どん」と呼ばれる場所には,室町時代から江戸時代の板碑と五輪塔が建っている。この岩屋には伝説が残っている。ある僧侶が,岩屋で法水(身体を清めるための水)を汲んで修行をしていたところ,1頭の鹿が来て法水 […]
- »2014年3月19日
- 上仙田東屋敷供養塔群
-
仙田瓦ヶ尾一帯は,昔,仙田村東屋敷と呼ばれていた。ここには,この地に住んでいた六兵衛(戒名は月秋浄井上座)が建立したと言われる六地蔵塔1基,五輪塔15基,板碑6基,その他多数の供養塔の残欠が残っている。元和8年(1622 […]
- »2014年3月19日
- 興玉神社(九玉大明神)の棟札
-
興玉神社には,江戸時代の棟礼が5枚残っている。最も古いのは,天文5年(1536)12月20日と記された棟礼。これは頴娃氏第4代兼洪の時代のもので,頴娃氏の延命(長生き)・子孫繁昌・武運長久(戦に勝つ運命が長く続くこと)・ […]
- »2014年3月19日
- 上野神社周辺供養塔群
-
上野神社周辺には,「上野どんの墓」と呼ばれる百数十の供養塔群がある。供養塔群の中心には,比翼塚(愛し合って死んだ男女を一緒に葬った塚)ともみられる2墓の宝塔があり,し周囲に五輪塔や板碑等が並び,丘をつくっている。
- »2014年3月19日
- 長崎鼻
-
青い空に,紺碧の海へ続く黒い岩礁。指宿を代表する観光地の一つ長崎鼻。約2kmの岬の,海に突き出した奇岩突端付近では,溶岩が流れ出た模様がみてとれる。約10万年前に噴火した阿多カルデラより,さらに古い火山噴火の名残だ。ちな […]
- »2014年3月19日
- 頼宋塚・九郎塚
-
地元の人々に頼宋塚(デスドン),九郎塚(クロドン)と呼ばれる2つの塚には,次のような話が伝えられている。「頴娃6代城主兼堅の子・九郎と,兼堅の側室の子・小四郎という弟との間で,頴娃家の相続争いが起こった。小四郎の母親は九 […]
- »2014年3月19日
- 瑞応院中興開山舜請の墓
-
舜請法印(※法印:僧の最上位の役職名)は,正中3年(1326)に瑞応院を再興した。舜請は,応永27年(1420)11月27日,131歳で亡くなったといわれる。墓は枚聞神社神社の東に建てられ,3基の宝筐印塔の中央にある。他 […]
- »2014年3月19日
- 瑞応院跡
-
枚聞神社の西側一帯には,江戸時代まで瑞応院という枚聞神社の別当寺(神社に付属していた寺)があった。瑞応院は,僧正智通によって,白雉3年(652)開山,その後,数百年の間廃寺となっていたが,正中3年(1326),島津氏が舜 […]