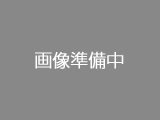瑞応院跡
- 歴史
- 近世・近代
- 枚聞神社
枚聞神社の西側一帯には,江戸時代まで瑞応院という枚聞神社の別当寺(神社に付属していた寺)があった。瑞応院は,僧正智通によって,白雉3年(652)開山,その後,数百年の間廃寺となっていたが,正中3年(1326),島津氏が舜請和尚に再興させた。瑞応院には,島津元久,家久公の位牌が安置され,頴娃郷の菩提寺でもあったと伝えられる。本尊は,廃仏毀釈の難をさけるため石棺に埋め隠されたが,明治12年に掘り出され,現在は,坊津久志の広泉寺に安置されている。
- 指定
- 市指定史跡
- 住所
- 開聞十町1406-1

より大きな地図で エリアで散策:枚聞神社〜竜宮神社の玉手箱〜 を表示