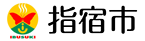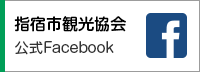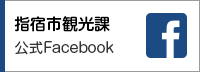令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付金)
更新日 2025年07月14日国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者および扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年10月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
支給対象者(支給要件)
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が指宿市であって、不足額給付Iまたは不足額給付IIのいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る)
不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したことなどにより令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりません。
【対象となる例(不足額給付I)】
●令5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
●子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
●当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付II
給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
ここでの低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
【対象となる例(不足額給付II)】
●令和6年度住民税において本人及び扶養親族等として定額減税対象外で、令和6年分所得税においても税制度上扶養親族等として対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合:4万円支給
●令和6年度住民税において本人及び扶養親族等として定額減税対象外で、令和6年分所得税においては税制度上扶養親族等として対象、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合:1万円支給
通知文書発送時期
対象となる方へ、確認完了後、発送します。(7月下旬以降、順次)
支給対象者と思われる方で,案内書類が届かない場合は,下記お問合せ先へご連絡ください。
受給に係る手続き(不足額給付I・II 共通)
〇「支給のお知らせ」が届いた場合:
記載された口座情報を確認し、変更が必要ない場合、手続き不要です。変更が必要な場合は同封の「口座登録等の届出書」に記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
〇「支給確認書」が届いた場合:
支給を希望する場合は、必ず、支給確認書に口座番号等必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
提出期限:令和7年10月10日(金)※締切日までに手続きがない場合は、辞退されたものとします。
その他
〇本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
〇給付金を装った"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
地域福祉課 社会福祉係 TEL 0993-22-2111(内線 2276)