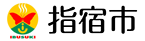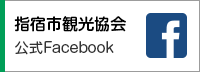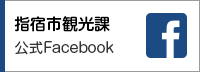家屋について
更新日 2025年11月14日家屋評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。その評価は3年(評価替え年度)ごとに見直されます。
新築家屋の評価
【評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率】
※再建築価格・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、評価替えの年(3年ごとの評価の見直し)時点において、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動割合を考慮します。なお、評価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
また、評価替えの年(基準年度)以外は、原則として、前年度の評価額に据え置かれることとなりますが、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
【在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合】
家屋を新増築された方
家屋を新増築された方へ
本年中に新増築された家屋は、翌年度から毎年固定資産税・都市計画税(都市計画税対象地域)の対象となります。税率は固定資産税が評価額の1.4%、都市計画税が0.1%です。
完成後、家屋調査をする必要がありますので、ご連絡ください。
家屋の評価方法について
市内に建築された家屋について実地調査を行い、固定資産評価基準によって家屋の評価額を算定します。
- ○評価の対象となるもの
- 屋根・基礎・外壁・内壁・柱・造作・天井・床・建具・建築設備(電気・給水・排水・衛生設備等)
- ○評価の対象とならないもの
- カーテン・家具(建物に固定していないもの)・冷暖房機器(天井・壁等に埋め込んでおらず取り外しが簡易なもの)・庭・門・ウッドデッキ・カーポート(壁が3面ないもの)
不動産取得税(県税)について
土地・家屋を取得したとき一度だけ課税されます。
○土地・・・取得してから3年以内に住宅を新築した場合は、申請することで減額制度が適用されます。
○家屋・・・新築住宅が特例適用住宅等の要件に該当する場合は、県の評価額から一定額の控除が受けられます。詳細は、鹿児島県南薩地域振興局 県税課(0993-52-1317)へお問い合わせください。
住宅借入金等特別控除(国税)について
住宅ローンを利用してマイホームを取得したり増改築したりしたとき、一定の要件を満たす場合には、居住した年から所得税が軽減されます。詳細は指宿税務署(0993-22-2548)へお問い合わせください。
新築家屋に対する減額措置
新築住宅(併用住宅・アパート等も含む)については、次の要件を満たすと、居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。
1 専用住宅や併用住宅であること。
併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
※併用住宅とは、居住の用に供する建物空間(居住部分)と、店舗、事務所など業務の用に供する建物空間(業務部分)とが合わさって、一つの建物となっている建物のこと
2 床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては 40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分 などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が 120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
| 一般住宅分 | 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
| 長期優良住宅分 | 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
未登記家屋の所有権移転及び家屋滅失届
登記されている建物の所有権移転等については、法務局から市への通知で把握できますが、未登記家屋の所有権移転や滅失など異動があった場合、市では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
固定資産税については、1月1日現在の所有者が納税義務者となりますので、未登記家屋の所有権移転や家屋の取り壊しがあった場合は、速やかに家屋所有者変更届及び所有者変更を証明する書類又は家屋滅失届を提出してください。
なお、1月2日以降に家屋を譲渡したり、家屋を取り壊したりしても、その年は1月1日時点の所有者に課税されます。したがって,納付書を旧所有者と新所有者の2通に分けて発行したり、月割で還付することはありません。
未登記家屋の名義を変更した場合
◆届出様式
◆添付書類
| 相続の場合 | 以下のうちいずれか1つ ・遺産分割協議書 ・戸籍謄本の写し ※旧所有者と新所有者の関係が分かるもの |
|||||||
| 売買の場合 | ・売買契約書等の写し ※旧所有者の実印が押印されたもの ・旧所有者の印鑑証明書の写し |
|||||||
| 贈与の場合 | ・贈与証書等の写し ※旧所有者の実印が押印されたもの ・旧所有者の印鑑証明書の写し |
|||||||
家屋を取り壊した場合
◆届出様式
受付場所
・税務課固定資産税家屋係
・山川・開聞支所市民福祉課市民税務係
固定資産税減額措置について
1 住宅耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成25年1月1日から令和4年3月31日までの間に、50万円を超える耐震改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度から一定期間において改修家屋の固定資産税が120平方メートルを限度として2分の1減額されます。
2 高齢者等が居住する住宅改修に伴う減額(バリアフリー改修)
新築された日から10年以上経過し、高齢者や障害のある方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)に、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの)を行った場合、工事が完了した翌年度の固定資産税が100平方メートルまでを 限度として3分の1減額されます。
3 省エネ改修に伴う減額
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の省エネ(熱損失防止) 改修工事(補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの)を行った場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートル分までを限度として3分の1減額されます。
※ これらの減額を受けるためには、申告が必要です。詳細についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)