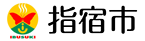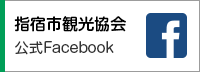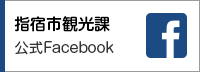国民健康保険・年金
-
国民健康保険の制度について知りたい。
国民健康保険は、病気やけがをしたときに経済的な負担を軽くし、安心して治療を受けられる制度です。
1.対 象 :職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。
2.保険税 :保険税は病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの費用にあてられます。保険税は必ず納期までに納めましょう。納付には便利な口座振替を利用してください。
3.介護保険:介護保険の第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)で、国民健康保険に加入している人の介護保険料も、国民健康保険税と一緒に徴収されます。 -
国民健康保険の脱退方法について知りたい。
次の場合は14日以内に国保介護課健康保険係、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係へ届け出てください。なお、75歳になって後期高齢者医療制度に加入するときは、届け出は不要です。
○ほかの市区町村へ転出するとき
○職場の健康保険(社会保険等)に加入したとき
○社会保険などの扶養家族になったとき
○死亡したとき
○生活保護を受けるようになったとき -
人間ドック検診料の一部補助を受けたいのですが、どうしたらいいですか。
国民健康保険、後期高齢者医療保険では人間ドックの一部補助を行なっています。
毎年、募集案内を4月号の広報紙に掲載します。
申し込みや、詳細については上記の募集案内を確認してください。 -
国民健康保険被保険者で、コルセット等の補装具を作ったのですが、払い戻しは受けられますか。
直接保険がききませんので、後で「療養費」として申請すると、その内容を審査して決定した額の7~9割を国保介護課から払い戻します。
-
国民健康保険被保険者で、月々の入院・通院等の自己負担が高額で、病院等への支払いが難しいのですがどうすればいいですか。
70歳未満で一部負担金の支払いが困難な人などには、経済的負担の軽減を図る目的で、入院の場合は「限度額適用認定証」、通院の場合は「国民健康保険高額療養資金貸付」という制度があります。
この制度は、自己負担限度額だけを病院等へ支払い、自己負担限度額を超えた高額療養費に相当する金額を指宿市が直接病院等へ支払うものです。 -
国民健康保険被保険者で、病院等へ搬送されたときに、その費用の払い戻しが受けられると聞いたのですが。
加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されますが、次の場合は対象外となります。
【支給対象外となるもの】
(1)緊急を要さない移送
(2)寝台車以外の移送
(3)飛行機での移送
(4)通院のための移送(往復も含む)
(5)退院のための移送
(6)入院にならなかった緊急の移送
(7)入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送 -
国民健康保険や後期高齢者医療などの保険証を紛失してしまった場合、再発行の手続きはどのようにすればいいですか。
次のような場合には、国民健康保険証の再交付が受けられますので、印鑑、身分証明書(運転免許証など)を持参し、国保介護課健康保険係または、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係で申請してください。
◆外出時に紛失したとき、盗難にあったとき
※早急にお近くの交番まで紛失届を出してください。
◆家の中で紛失したとき、破損、汚損したとき -
12月31日付で会社を退職し、1月1日以降国民健康保険に加入したいのですが、市役所が閉まっています。その間に病気等で病院へかかる際はどのようにすればいいですか。
医療機関窓口で、1月1日から国民健康保険加入予定であることを伝え、受診の上、医療費全額を支払ってください。
その際、後日保険証を提示することにより、保険診療に切り替えてもらえるかを確認してください。
※保険診療に切り替えるときは国民健康保険加入手続き後、保険証を医療機関へ持参し、払い戻しを受けてください。
※切り替えられない時は、受診後に支払った費用の領収書、診療報酬明細書(レセプト)を受け取ってください。 -
退職者医療制度とはどのようなものですか。
退職者(被扶養者含む)が、それまで加入していた社会保険(社保)から、国民健康保険(国保)に加入したとき、一定の手続きをすると、受診した医療費の一部を社保が負担し、結果的に国保の財政負担が軽減される制度です。
この制度は、国保に加入した退職者が受診した場合に、窓口で支払う一部負担金の額(原則として3割)や、保険税額について変更はありませんが、国保の財源を確保する上で大変重要なことです。厳しい国保財政を改善する一助として、ご協力をお願いします。 -
特定疾病とはどのようなものですか。またその申請はどのようにすればよいのですか。
厚生労働大臣の定める疾病で、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全等です。病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、病院等へ支払う金額は一つの病院ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
ただし、70歳未満の上位所得者については、限度額が2万円となります。また、入院した場合には、食事代や差額ベッド代等の保険適用外の費用が別途請求されます。
-
人間ドックと特定健康診査の両方を受診することはできないのですか。
人間ドックを受診した場合は、特定健康診査を受けたことになります(受診内容が同じ)ので、どちらか一方のみの受診となります。
-
保険の種類にはどのようなものがありますか。
医療保険は、会社などに勤める人が職場で加入する「職域保険」と、その地域に住み、職域保険の対象とならない人を対象とした「地域保険」の2つに分かれます。
【職域保険】
(1)一般の職場を対象とした健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会)
(2)船員のための船員保険
(3)公務員や私立学校教職員を対象とした各種共済組合地域保険【地域保険】
(1)市町村居住者を対象に、市町村が保険者となる国民健康保険
(2)同種事業者とその従事者・家族を対象にした国民健康保険組合
(3)県内居住者で75歳以上の人及び65歳から74歳までの人で一定の障害のある人を対象にした後期高齢者医療